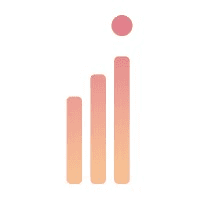運用型広告とは?基本の定義と仕組み
運用型広告とは、広告主側で以下のような複数要素を調整しながら出稿できる広告手法のことです。
出稿目的
配信ターゲット
出稿期間
配信タイミング
予算
表示するテキストや画像などのクリエイティブ
運用後はインプレッション数やクリック率といった数値を測定し、「ターゲットにマッチしたクリエイティブを配信できたか?」「アプローチの頻度は適切か?」などをチェックすることで、自社の目標達成につながる広告へと改善していきます。
運用型広告の出稿では、入札を実施する「オークション形式」という仕組みが採用されています。具体的な流れは以下のイメージです。

入札額だけでなく、以下のような「クリエイティブのクオリティ」も結果に影響を与えます。そのため、予算が少ない企業でも広告を出稿できる可能性がある点が魅力です。
広告のテキストがターゲットにマッチしているか?
適切なLP(ランディングページ)へ遷移しているか?
画像やデザインの視認性は優れているか?
検索キーワードのニーズとマッチしているか?
もちろん、より詳細な出稿の決め方は媒体ごとで異なるため、上記はあくまでも目安と捉えてください。
予約型広告(純広告)との違い
運用型広告と予約型広告(純広告)の主な違いは、以下の通りです。
【運用型広告】
出稿の成果を計測しながら、入札額や掲載場所、出稿期間、配信ターゲット、配信頻度、クリエイティブの内容などを、広告主側で調節できます。成果に合わせ広告のアプローチ方法を変更できるため、改善を繰り返すことで最大限の効果が得られるかもしれません。
【予約型広告(純広告)】
各媒体の掲載枠を買い取って、広告を出稿します。買い切りであるため、一定期間はほぼ確実に広告を掲載し知名度を高められる点が魅力です。また、運用の必要性がないため、自社と親和性が高い枠に広告を掲載できれば、少ない労力で大きな成果を残せるかもしれません。
ただし、運用型広告のように、効果を測定しながら配信ターゲットを修正したり掲載場所を変えたりといった柔軟な対応はできません。そのため、具体的なターゲットのコンバージョンにつなげるより、知名度獲得に利用することが一般的です。
なぜ今「運用型」が主流になっているのか?
運用型広告は、2024年12月時点の日本のデジタル広告市場において「87.4%」も導入されており、主流な配信方法となっています。
参照:総務省|広告主等向けガイドラインの構成について p.5
運用型広告がこれほど主流になっている理由として、主に以下2つが挙げられます。
配信技術が進化し自社ターゲットへアプローチしやすくなった
効果測定を実行し正しい方向性で改善しやすい
(媒体によって差はありますが)運用型広告では「性別・居住地域・年代・利用デバイス・興味関心・サイト上の行動履歴」といった条件で、配信対象を細かくセグメント分けできます。配信対象を絞り込むほど自社ターゲットへリーチしやすくなるため、必要最低限の広告費用で効率的にコンバージョンへつなげられる可能性があるのです。
また、運用型広告では、クリック率やコンバージョン率、インプレッション数、クリック単価などの指標を活用して効果測定もできます。数値をもとに広告の成果を定量的に計測することで、自社の目標に向けて正しい方向性で運用方法を改善できるでしょう。
運用型広告の主な種類
運用型広告の種類としては、主に以下が挙げられます。
リスティング広告(検索連動型広告)
ディスプレイ広告(バナー広告)
SNS広告(Instagram・X・TikTokなど)
動画広告(YouTubeなど)
ショッピング広告(ECサイト向け)
媒体ごとで配信ターゲットが異なるため、自社のユーザー層を踏まえて配信先を決めることが大切です。
リスティング広告(検索連動型広告)
「リスティング広告(検索連動型広告)」とは、GoogleやYahoo!などでの検索ワードを踏まえ、検索結果画面にテキストで出稿できる広告のことです。以下のように、主に「記事のURL・タイトル・説明文」を表示できます。

「検索結果画面の一番上部」に掲載できるため、キーワードのニーズにマッチする適切なクリエイティブを表示できれば、多くのサイト流入が期待できます。
リスティング広告は、最低出稿金額の公式な規定はありません。日予算は任意に設定でき、少額から開始できます。「初めて運用型広告を使うので成果を出せるか不安」「中小企業なのであまり予算を投下しにくい」といった企業でも使いやすい点が魅力です。
リスティング広告の具体的な特徴や向いているケース、出稿方法などについては「リスティング広告とは|費用や仕組みを徹底解説【初心者向け】」で解説しています。
ディスプレイ広告(バナー広告)
「ディスプレイ広告(バナー広告)」とは、以下のようにWebサイトやアプリに設けられた枠に出稿する広告のことです。画像や動画、テキストを組み合わせてバナー広告のように作成します。

画像や動画を利用し、視覚的に自社サービスや商品をアピールできます。固定の広告枠へ配信するため、特定ターゲットへのアプローチは難しいかもしれません。しかし、まだ自社と接点を持たない潜在層へ、効果的に認知拡大できる可能性もある点が魅力です。
SNS広告(Instagram・X・TikTokなど)
SNS広告とは、InstagramやX、TikTokなど、各SNS上に出稿する広告のことです。主にテキストや画像、動画、リンク、ハッシュタグを広告に活用できます。
SNS広告では、フォローアカウントや閲覧履歴、ターゲットの特性といった基準で、配信先を細かくセグメント分けしたうえで出稿可能です。特定の層へ的確にリーチできるため、コストを最小限に抑えつつ、自社と親和性が高いターゲットへピンポイントでアプローチすることが期待できます。
また、Xのリポストのように、SNSではユーザーによって拡散される可能性もあります。そのため「シェアしたい」と思われる高品質な広告を出稿できれば、自然と拡散が行われて、自社で追加コストを投下せずとも認知度の拡大や新規顧客の獲得などを実現できるかもしれません。
SNS広告がオススメな企業の特徴や導入メリット、各媒体の詳細などについては「SNS広告とは|各SNS広告の特徴、費用、選び方を解説」で解説しています。
動画広告(YouTubeなど)
「動画広告」とは、YouTubeやSNS(XやTikTokなど)、各種アプリなどに動画で出稿する広告のことです。映像やアニメーション、音声を駆使してクリエイティブを制作できるため、テキストや画像より効果的にユーザーの印象に残せます。
とくに動画広告の代表であるYouTubeは、幅広い世代で高い利用率を保っており、利用者の7割以上に達します。潜在顧客や見込み顧客、新規顧客、既存顧客といった幅広いユーザーへ効果的にアプローチできる点が魅力です。
YouTube広告の場合、課金については「一定時間以上広告が視聴された」 「ユーザーが企業サイトへ遷移した」などのタイミングで発生します。一定の効果が表れた場合にコストが発生するため、高い費用対効果が期待できるかもしれません。
動画広告の中でも知名度が高いYouTube広告については、「YouTube広告とは?広告種類から目的に応じた選び方、出稿方法まで徹底解説」で解説しています。
ショッピング広告(ECサイト向け)
「ショッピング広告」とは、ECサイト向けに運営されている広告のことです。以下のように、Googleの検索結果画面の上部や右側、ショッピングタブ、画像検索結果といった場所に、商品画像や価格、販売店舗名などを表示できます。

商品を検索済みで購買意欲が高いユーザーへ視覚的にアピールできるため、コンバージョン率の向上が期待できます。
また、ショッピング広告は、Google Merchant Centerに登録した商品データ(商品名・価格・画像・在庫状況など)を参照し、広告を自動生成する仕組みを構築しています。そのため、検索キーワードを手動で設定する必要がありません。担当者の負担を軽減しつつ、購買意欲が高いユーザーへアプローチできるというのは魅力的です。
ショッピング広告の具体的な仕組みや費用、活用前に知っておくべきポイントなどについては「ショッピング広告で売上を伸ばす|仕組み・費用・活用のポイントを解説」で解説しています。
運用型広告のメリット・デメリット
運用型広告には、以下のようなメリット・デメリットがあります。両方を把握し、自社にとって最適な手法を選ぶことが大切です。
メリット
運用型広告のメリットとして、大きく以下が挙げられます。
クリック数やコンバージョン率などをもとに効果測定し改善しながら運用できる
広告の出稿内容を柔軟にカスタマイズできる
細かい精度でターゲティングし自社と親和性が高いユーザーへアプローチできる
少額から運用をスタートできる
運用型広告では、(媒体にもよりますが)クリック数やコンバージョン率、インプレッション数、クリック単価などの指標をチェックできます。数値で定量的に測定できるため、「クリック率が低いのでキャッチコピーを見直す」「購入につながっていないので遷移先のLPを見直す」というイメージで、目標達成に向けて改善を積み重ねられます。上記と関連し、効果測定の結果をもとに配信日時や地域、配信頻度なども柔軟にカスタマイズ可能です。
また、細かい精度でターゲティングできる点も魅力です。例えば、リスティング広告なら「ユーザーの興味・広告の配信先デバイス・配信地域など」、SNS広告なら「フォローアカウント・閲覧履歴など」でターゲティングできます。自社がアプローチすべきユーザーに近い層へ広告を表示できるため、必要最低限のコストで大きな成果を残せるかもしれません。
また、運用型広告では、クリック数や表示回数といった一定の成果に応じて課金が発生します。成果に伴いコストが高くなる仕組みであるため、「まずは少額から運用して成果が出たら予算を増やす」といった柔軟な運用が可能です。予約型広告のように「大きな予算を支払ったが思うように成果が出なかった」といった事態を防げるため、運用に大きな予算を投下できない企業にもオススメです。
デメリット
一方で、運用型広告のデメリットとして、大きく以下が挙げられます。
継続的にPDCAサイクルを回す意識が必要になる
社内で運用に投下するリソースを確保しなければならない
広告運用の専門知識を持たないと費用対効果が下がるケースがある
運用型広告では、一度目の施策でいきなり理想の成果を出せるとは限りません。成果を出すには「ターゲットを設定する→クリエイティブを制作して出稿する→成果をもとに次回以降の改善策を考える」というサイクルを回す必要があるため、長期的な運用が必要です。
上記と絡めて、社内で広告運用を担当できる人員や予算を確保する必要があります。しかし、広告運用では「ターゲットを踏まえて配信先を絞り込める」「ターゲットのニーズに刺さるクリエイティブを制作する」などの専門知識が必要なため、すべての企業で適切な人員を確保できるとは限りません。もし専門知識を持つ人材がいなければ、PDCAサイクルを回すスピードが低下するため、思うように成果を残せない可能性もあります。
運用型広告の始め方の基本的な手順
運用型広告の始め方の手順は、厳密には広告媒体ごとで異なります。しかし、大まかには以下の手順に沿って進めればOKです。
Step.1 出稿目的やKPIを設定する
Step.2 アプローチすべきターゲットを設定する
Step.3 出稿する媒体を選定する
Step.4 ターゲットを意識してクリエイティブを制作する
Step.5 入稿後に配信の詳細を設定し運用を開始する
Step.6 数値をもとに効果測定を行い次回以降の改善策を設計する
Step.1 出稿目的やKPIを設定する
最初に広告の出稿目的を設定しましょう。以下のように具体的な目的を決めることで、適切なターゲット設定やクリエイティブ制作などを進める際に役立ちます。
自社サイトへの流入数を増やしたい
ECサイトの登録者数を増やしたい
新商品の認知度を高めたい
成約確度が高い顧客からの問い合わせ数を増やしたい
目的については「会員登録者数を前年比で◯◯%増やす」といったイメージで、数値で設定してください。最終的なゴールを数値で設定しておけば、中間目標(KPI)を考える際に、具体的なギャップを洗い出し「いつまでに・どの数値を・どのくらい改善すべきなのか?」という点を明確に判断できます。
KPIの設定で活用できる指標としては、自社サイトの訪問ユーザーの中でコンバージョンを達成した割合を表す「CVR(コンバージョンレート)」や、ひとりの顧客獲得に投下した単価を算出した「CPA」などが挙げられます。
Step.2 アプローチすべきターゲットを設定する
出稿目的を決めたら、アプローチすべきターゲットを設定します。ターゲットについては、以下のような項目を踏まえて、具体的なペルソナまで落とし込むことが大切です。
名前/年齢/性別/職業/収入/学歴/家族構成/居住地/性格(価値観・人生観)/趣味/余暇の過ごし方/人間関係(友人の数など)/習慣/買い物をする場所 , etc. |
具体的なペルソナを設定することで、広告出稿時に配信先のセグメント分けを実施する際、絞り込む項目を明確に判断できます。
具体的なペルソナの設計方法については「ペルソナの作り方は?マーケティング業務で活用するポイントも解説」で解説しています。
Step.3 出稿する媒体を選定する
次に、目的や配信ターゲットに合わせて、広告の出稿媒体を選定します。運用型広告は媒体ごとでアプローチできる層が異なるため、適切なユーザーが利用する媒体へ出稿すれば、高い費用対効果を実現できます。例えば、SNS広告の中でも「TikTok広告」は10代および20代の利用率が高いため、若年層向けサービスの広告を出稿する際に適切です。あるいは、短期的な売上アップを目指すのであれば、検索キーワードをもとに購買意欲が高いユーザーに絞ってアプローチできる「リスティング広告」が効果を発揮するかもしれません。
Step.4 ターゲットを意識してクリエイティブを制作する
以下のようなポイントを意識しながら、目的やターゲットを意識したクリエイティブを制作してください。
リンク先の内容を適切な文章で説明できているか?
ターゲットが思わずクリックしたくなるキャッチコピーを使っているか?
商品の特徴だけでなく利用のメリットをコンパクトに伝えられているか?
画像や動画を駆使して視覚的にターゲットに刺さるよう工夫しているか?
ターゲットが好むデザインや色使い、テキストの配置などを意識しているか?
広告媒体によっては、クリエイティブ制作に関するガイドラインを規定しているため、必ずチェックしてください。万が一、ガイドラインに沿わないクリエイティブを制作すると、広告を出稿できないケースもあります。
例えばLINE広告であれば、化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)に関するサービスの広告を出稿する場合、「承認等外の効能効果を暗示・明示する表現」「人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現」などは認められていません。
参照:LINEヤフー for business|LINE広告審査ガイドライン
Step.5 入稿後に配信の詳細を設定し運用を開始する
クリエイティブを入稿したら、以下のように配信の詳細を設定し運用を開始します。
Step.6 数値をもとに効果測定を行い次回以降の改善策を設計する
出稿の効果を数値で測定し、想定通りの成果が出なかったポイントを洗い出して、次回以降の改善策を設計してください。効果測定で「なぜクリック率が低いのか?」「なぜ流入はあるのに購入につながらないのか?」といった問題点を抽出し、原因をピンポイントで解決できる施策を設計することで、自社の目標達成の確率が高まります。
業界や業種別にチェック!運用型広告の活用ポイント
運用型広告の活用ポイントは、業界や業種、商材の種類などによって異なります。ここでは、主要な以下6つにおけるポイントをまとめました。自社にマッチする部分がないか、ぜひチェックしてください。
小売業界
ECサイト
不動産などの高額商材
BtoBサービス全般
飲食・美容などの店舗型ビジネス
教育業界
小売業界
小売業界では「SNS広告」を活用した購買促進が効果的です。小売業界では、個人の消費者へ直接商品を販売することが一般的です。そして、この個人の消費者は「SNS上の投稿を見て商品を比較検討する」「拡散されてきた新商品やキャンペーン情報をもとに商品を認知する」というように、SNSを活用することが考えられます。このように、SNSと親和性が高い個人へSNS広告で商品をアピールできれば「興味を持たれてフォローしてもらう」「その場で購入を即決してもらう」などにつながることが期待できます。
ECサイト
ECサイトを運営する場合は「ショッピング広告」の活用がオススメです。ショッピング広告であれば、ユーザーの検索結果画面にECサイトの商品画像や価格、販売店舗名、レビューなどのスペックを表示し、直接サイトへ遷移できます。商品画像を活用して魅力を効果的にアピールできるため、検索ユーザーの購買意欲を刺激して購入へつなげやすい点が魅力です。無料の広告掲載枠も用意されているため、初めて運用型広告を実施したい企業でも安心です。
不動産などの高額商材
不動産などの高額商材の場合は、「リスティング広告を活用したリマーケティングによるリード獲得」がオススメです。
前提として不動産などの高額商材の場合、顧客が購入を即決するケースはほぼありません。支払い額が大きいため、以下のように時間をかけてじっくり検討することが一般的です。
各社の資料をダウンロードして比較検討する
担当者から詳細をヒアリングする
社内で検討して決裁者の判断を仰ぐ
そのため高額商材を販売する場合は、いきなり購入を迫るのではなく、上記のようなフェーズに合わせて情報を提供して、少しずつ自社への興味や信頼性を構築する「リードナーチャリング」が必要です。
リスティング広告とリマーケティングを組み合わせれば、「サイトを訪問したユーザーへ後日改めて商品の広告を表示する」といったイメージで、一度自社へ興味を持った顧客へ無理なくアプローチできます。顧客の検討段階に何度か広告が表示されることで、自然と自社への興味が醸成されて、最終的な購入につながるかもしれません。
BtoBサービス全般
BtoBサービスの場合は、SNS広告のひとつである「LinkedIn広告」の活用がオススメです。 LinkedInとは、ビジネス特化型のSNSのことです。顔出し・実名利用が原則であり、キャリアアップやビジネスで活用できる人脈などを求めるユーザーが多数登録しています。
そのため、対企業へ販売する「BtoB系の商材」との相性は高いことが期待できます。具体的には「広告経由でホワイトペーパーをダウンロードしてもらいニーズにマッチした情報を提供する」「ウェビナー集客用の広告を出稿してユーザーと接点を作る」といった形で運用可能です。
飲食・美容などの店舗型ビジネス
飲食・美容といった店舗型ビジネスの場合は、「エリアターゲティング広告を活用した予約誘導」がオススメです。
エリアターゲティング広告とは、ユーザーの位置情報を分析し特定の地域に絞った広告を配信する手法です。周辺地域や駅などで細かくセグメント分けできるため、店舗の最寄り駅周辺や「◯◯周辺 美容室」というように絞って検索するユーザーへ効率的にリーチできます。ユーザーは「特定の地域でお店を探したい」というニーズを持っているため、広告を表示できればスムーズに予約や来店へつなげられることが期待できます。
また、ユーザーの直近の現在地をもとに広告を表示するため、「現在開催している来店キャンペーン」「すぐに使えるクーポン情報」などの魅力的な情報を発信できれば、短期的な成果にもつながるかもしれません。
教育業界
教育業界の場合は、「YouTube広告による認知拡大」「リスティング広告経由による資料請求」という形での運用がオススメです。
まずYouTube広告を活用することで、動画を活用して授業風景や無料体験の様子、教室の雰囲気、教師の人柄、在校生の声などをわかりやすく伝えられます。視覚的に学習効果をイメージしてもらえるため、「子どもの将来に関わることなので慎重に塾を決めたい」などと考えている保護者からの信頼を獲得しやすいかもしれません。
また、「(地名)集団授業 塾」「オンライン 個別指導塾」などで検索しているユーザーは、明確に学習コンテンツを探していると予想できます。すでに購買意欲が高いユーザーへ、リスティング広告を活用し塾の無料体験や季節講習などをアピールできれば、短期的な資料請求や入塾などにつながる可能性があります。
運用型広告を成功させるためのコツ
運用型広告の取り組みを成功させるには、以下のようなコツを押さえることが大切です。
最初に配信の目的やKPIを設定する
ターゲットを絞り込んで配信する
小さく始めてクリエイティブ改善や配信設定の変更を繰り返す
長期的な視点で運用する
最新の媒体トレンドをキャッチアップする
社内リソースが不足している場合は代理店も活用する
最初に配信の目的やKPIを設定する
必ず最初に広告の目的およびKPIを設定してください。ゴールや達成までの中間目標を明確に定めておくことで、ギャップを具体的に把握し「どの数値を・いつまでに・どのくらい改善するために・どんな施策を実行すべきか?」を的確に判断できます。
ゴールや中間目標については、以下のように数値で設定してください。
商品の売上を前年度比で◯◯%アップを達成する
来年中までに会員登録者数を××倍まで増やす
来期までにクリック率を◎◎%増やす
数値で目標を設定しておくことで、ゴールまでの差を定量的に把握できます。
ターゲットを絞り込んで配信する
運用型広告では、ターゲットを絞り込んで配信してください。配信のアプローチ先を絞り、サービス利用や商品購入につながりやすいユーザーへリーチすることで、必要最低限のコストで高い売上を残せる可能性があります。ターゲットを絞り込む際は、年齢や居住地域、性別、過去の閲覧履歴、興味・関心、検索キーワードなどを活用してください。
また、絞り込みだけでなく「配信先からの除外設定」も大切です。除外設定とは「類似しているだけで自社商品とは関連性が低いキーワード」「検索されているが購入につながる可能性は低いキーワード」などの条件で、特定ユーザーを配信先の対象から外すことです。成果につながりにくいユーザーへの広告配信を避けることで、「関係ない広告ばかり表示されて自社への印象が悪くなる」「コンバージョンの見込みが低いユーザーがクリックしてしまいコストばかり膨らむ」などの事態を回避できます。
小さく始めてクリエイティブ改善や配信設定の変更を繰り返す
運用型広告では、施策の成果をもとに改善点を洗い出し、長期的な視点でブラッシュアップすることが大切です。そのため、まずは少額から始めて少しずつ運用成果をチェックし「LPのクリック率が低いのでキャッチコピーを修正する」「配信のタイミングを修正する」といったイメージで、長期的に改善を繰り返してください。
改善の際は「A/Bテスト」を実施することも必要です。A/Bテストとは、クリエイティブの一部を変えた複数の広告を運用し、それぞれの成果の違いを計測する手法のことです。例えば、広告A・Bを用意して「A・Bのデザインは同じだがキャッチコピーだけ変える」「A・Bの広告内容は同じだが配信のタイミングのみ変える」などのイメージで出稿条件を変えることで、それぞれの効果を計測し理想的な広告へとブラッシュアップできます。
長期的な視点で運用する
上記で解説したように、運用型広告で成果を出すには長期的な視点での運用が必要です。
確かに短期的には、広告の出稿費用やクリエイティブの制作費、スタッフの人件費などが膨らむため、費用対効果が低下したように感じるかもしれません。しかし、広告によって商品の売上アップや会員登録者数の増加などを実現できれば、長期的には自社の業績アップに大きく貢献します。
成果が出るまでの目安期間は業界・業種ごとに異なるため一概にはいえませんが、数週間〜数ヶ月レベルでの運用が必要なことは事前に想定しておいてください。
最新の媒体トレンドをキャッチアップする
運用型広告では、媒体のトレンドが日々変化しています。例えば、直近のトレンドでいえば「縦型ショート動画の反応が好調である」「AIを駆使したことでターゲティングの精度が向上している」などが挙げられます。広告を出稿するうえでは、こうしたトレンドを適宜キャッチアップし、自社サービスや商品と親和性が高い広告を設計する際の参考にすることが重要です。
社内リソースが不足している場合は代理店も活用する
運用型広告の施策を実行するには、以下のような取り組みが必要です。
出稿の目的を決めて媒体を選定する
アプローチすべきターゲットを詳細に決める
ターゲットに刺さるクリエイティブを制作する
出稿の成果を計測して次回以降の改善策を練る
上記のような取り組みでは専門知識が必要なため、どうしても「社内に専門的な人材がいない」「教育するコストや余裕がない」という企業もあるでしょう。
社内のリソースが不足している場合は、広告代理店へ運用を依頼することも有効です。広告代理店であれば、豊富な専門知識をもとに自社にとって最適な広告を制作し、運用してくれます。もちろん依頼にはコストがかかりますが、プロの手を借りてスピーディに成果を出し将来的な業績アップにつなげられるため、長期的な費用対効果は高くなると期待できます。