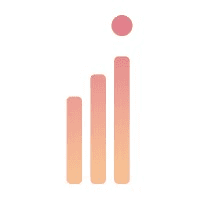共感マーケティングとは
まずは共感マーケティングの基本概念を整理し、従来のマーケティング手法との違いを明確にします。なぜ今、共感が重要視されているのか、その背景から理解していきましょう。
定義と位置づけ(エモーショナルマーケティングとの違い)
共感マーケティングとは、顧客の価値観や体験、感情に寄り添うことで、ブランドと顧客の間に深い結びつきを創出するマーケティング手法です。
「エモーショナルマーケティング」としばしば混同されますが、両者には以下のような違いがあります。
エモーショナルマーケティング
感情を"刺激"することに重点
一時的な感情の高まりを狙う
商品購入時点での感情的反応を重視
共感マーケティング
価値観や体験を"共有"することに重点
持続的な関係性の構築を狙う
購入前後を通じた継続的な共感関係を重視
共感マーケティングは、顧客が「この企業は私のことを理解してくれている」と感じる状態を意図的に設計し、長期的なブランドロイヤルティの向上を目指します。
共感が注目される背景(SNS時代の購買行動・価値観の変化)
共感マーケティングが注目される背景には、デジタル時代における消費者行動の根本的な変化があります。
情報過多による選択疲れ
現代の消費者は、日々膨大な商品情報に触れています。機能面での差別化が困難になった結果、「何を選ぶべきか」から「なぜこのブランドを選ぶのか」という判断軸にシフトしています。
SNSによる価値観の可視化
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSプラットフォームでは、個人の価値観や体験が日常的に共有されます。企業も同様に、ブランドとしての価値観や姿勢を明確に示すことが求められるようになりました。
体験価値への重視
特にミレニアル世代以降の消費者は、商品そのものよりも「その商品を通じて得られる体験」や「そのブランドと関わることで表現できる自分らしさ」を重視する傾向が強まっています。
共感マーケティングと従来型マーケティングとの比較

共感マーケティングは、従来型マーケティングと比べて訴求の“軸”が大きく異なります。従来は商品の機能や価格、利便性といった「モノの価値」を前面に打ち出し、不特定多数への一斉発信(マスマーケティング)を基本とする手法が主流でした。
一方、共感マーケティングでは「その商品が誰の、どんな感情や悩みに応えるのか」という感情ベースの価値訴求へと軸足が移っています。たとえば、価格ではなく「このブランドは私の価値観をわかってくれている」と感じさせるようなメッセージ設計が重視されます。
また、従来のKPIが短期的なCVRやクリック数だったのに対し、共感マーケティングでは**ブランドへの共鳴やLTV(顧客生涯価値)といった中長期的な関係性構築に重きが置かれています。
このように、商品軸から顧客軸、情報発信から対話、即時成果から長期信頼へと、マーケティングの構造自体が根本から変わりつつあるのが現在の潮流です。
共感マーケティングがもたらす3つの成果
共感マーケティングを導入することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、LTV向上、認知拡大、価格競争からの脱却という3つの主要な成果について詳しく解説します。

LTV(顧客生涯価値)の向上とファン化の促進
共感マーケティングの最も大きな成果は、顧客のLTV向上です。LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、一人の顧客が企業との関係を継続する期間中に、その企業にもたらす総利益のことです。「顧客生涯価値」とも呼ばれます。
共感によって結ばれた顧客は、単なる商品購入者から「ブランドのファン」へと変化します。
具体的な効果
リピート購入率の向上
客単価の増加(上位商品やオプションの購入)
解約・離脱率の低下
ブランドへの愛着度向上
これらの効果が生まれる理由は、共感によって築かれた関係が単純な取引を超えているからです。顧客は商品の機能だけでなく、ブランドの価値観や姿勢に価値を感じるため、多少の価格差があっても他社に流れにくくなります。また、ファン化した顧客は積極的にブランドを応援する存在となり、新商品発売時の初期顧客としても機能し、事業拡大の重要な基盤となります。
UGC・口コミによる低コストの認知拡大
共感を得た顧客は、自発的にブランドについて発信する傾向があります。これにより、企業の広告費をかけることなく、信頼性の高い口コミによる認知拡大が実現できます。
UGC(User Generated Content)の効果
友人・知人からの推薦による高い信頼性
広告感のない自然な商品紹介
多様な視点からの商品価値の発見
SNSでの拡散による広範囲への到達
このようなUGCが生まれる背景には、顧客の「このブランドを誰かに教えたい」という感情があります。UGC(User Generated Content)とは、企業ではなく一般のユーザー(顧客)が自発的に作成・投稿するコンテンツのことです。日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と呼ばれます。
共感を得た顧客は、ブランドとの関係を誇らしく思い、自分の体験を積極的にシェアします。特にInstagramやTikTokなどのビジュアル重視のプラットフォームでは、顧客が商品を使用している様子や、ブランドへの愛着を表現した投稿が自然に拡散され、新規顧客の獲得につながります。
従来の広告と比べて信頼性が高く、エンゲージメント率も向上するため、費用対効果の高い認知拡大が実現できるでしょう。
非価格競争への転換(ブランド選好の構築)
共感マーケティングによって差別化が図れると、価格競争から脱却し、「このブランドだから選ぶ」という状態を作り出せます。
非価格競争への転換効果
利益率の改善
競合他社との明確な差別化
ブランドプレミアムの確立
価格訴求に頼らない安定した事業運営
非価格競争への転換は、共感マーケティングの最も重要な成果の一つです。
顧客がブランドの価値観や哲学に共感すると、商品選択の基準が「最も安いもの」から「最も自分の価値観に合うもの」へと変化します。これにより、機能面では類似した商品であっても、ブランドの姿勢や想いに共感した顧客が継続的に選び続ける状況が生まれます。
結果として、価格競争に巻き込まれることなく適正な利益を確保でき、持続的な事業成長が可能です。
実際の導入企業に見る共感マーケティングの成功事例
理論だけでなく、実際に共感マーケティングで成果を上げている企業の事例を見てみましょう。各社がどのような共感軸を設計し、具体的にどんな施策を展開しているのか、参考になるポイントを抽出します。
AND PLANTS|「植物のある暮らし」に共鳴する世界観を可視化

引用:
AND PLANTS|観葉植物・お花の通販
観葉植物のD2Cブランド「AND PLANTS」は、"植物とともに生きるライフスタイル"というコンセプトを軸に、世界観設計とSNS戦略を融合させて成功した好例といえるでしょう。
同ブランドの共感ポイントは、まずブランドのビジョンやミッション(「グリーンのある心地よい暮らしを」)を明文化し、世界観を整えて発信している点にあります。単に商品自体の魅力を伝えるのではなく、「植物を迎えることがもたらす心の変化」にフォーカスしたストーリー設計を行っているのです。
また、Instagramや自社メディアでは、購入者が自宅で植物と過ごす様子(UGC)を積極的にシェアし、ブランドと顧客の共通体験を育成していることも特徴的でしょう。これにより、SNSのフォロワーが自然増加し、コンテンツからのコンバージョン率も向上しています。
さらにUGCの活用により、広告費を抑えながら信頼性のあるブランド認知を拡大することに成功しました。結果として「見た目の良い植物を買う」ではなく、「自分の暮らしを豊かにしたい」という価値観で選ばれるブランドへと進化を遂げています。
無印良品|企業理念を軸とした信頼構築

引用:無印良品
無印良品は、「生活の基本と普遍」を提供するという企業理念を軸に、消費者との共感を創出している代表例です。同社WEB事業部の川名常海部長は「理念に共感してもらい、つながった人たちと"会話"をすることで関係を深めていく」と述べており、共感マーケティングの本質を体現しています。
同ブランドの共感ポイントは、単なる商品説明ではなく「なぜその商品を作ったのか」という理念をすべての接点で語っている点でしょう。「足なり直角靴下」では自然な履き心地への想いを説明し、商品開発の背景まで丁寧に伝えています。
また、オウンドメディア「くらしの良品研究所」やアプリ「MUJI Passport」、コミュニティ「IDEA PARK」で顧客との双方向コミュニケーションを重視している点も特徴的です。評価指標として「いいね」「コメント」「アプリ起動数」などの"参加"を重視し、リーチよりも共感の深さを測定しています。
この結果、アプリ「MUJI Passport」は約1,000万ダウンロード、月間アクティブユーザー約720万人を獲得し、理念(WHY)→ ストーリー化(HOW)→ 顧客参加体験(WHAT)の流れで「ブランドへの共感」が購買行動に直結する好循環を構築しました。
出典元:良品計画の川名部長が語る「消費者の共感」を生む無印良品のデジタルマーケティング
Soup Stock Tokyo|“体温を届ける”ブランド設計と共感の連鎖

引用:Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)
Soup Stock Tokyoの共感マーケティングは、ブランド理念に根差した設計が特徴です。
「食べることは、生きること。」という言葉に代表されるように、スープを通じて生活者の心に温度を届けるという思想ベースのマーケティングを実行している企業です。
社長が語る「世の中の体温をあげる」という理念は、すべての施策に通底しており、単なる“飲食”ではなく、感情に働きかける体験価値の提供へと昇華しています。
Soup Stock Tokyoでは「秋野つゆ」というブランドを人格化した仮想の人物を設定し、彼女の目線に立って言葉・商品・店舗設計を行っています。
この共通の顧客像に基づくブランド運営により、全社的に一貫性のあるメッセージ設計が可能となりました。
Web・接客・パッケージなど、あらゆる接点で「同じ人格が語りかけてくる」状態が作られ、顧客との感情的な信頼関係を強固にする土台になっています。
また、母の日や春の七草など、季節や記念日に合わせたメニュー・キャンペーンは、すべて「社内の対話」から設計されています。
「この日はどんな想いを届けるか?」という議論を重ねることで、ただの販促ではなく、“意味のある体験”として顧客に届くという、内発的な共感設計プロセスが、ファンの信頼獲得につながっています。
共感マーケティングの導入ステップと設計フレーム
いよいよ実践編です。共感マーケティングを自社で導入する際の具体的なステップと、各段階で使える実用的なフレームワークを紹介します。
1. インサイト分析と共感ポイントの抽出
共感マーケティングの第一歩は、顧客の深層心理(インサイト)を理解することです。表面的なニーズではなく、その背景にある感情や価値観を深く掘り下げる必要があります。
インサイト分析では、まず顧客インタビューの実施が重要です。購買に至った理由だけでなく、「なぜその商品を必要と感じたのか」「どんな気持ちの変化があったのか」といった感情面まで聞き取ります。同時に、SNSでの顧客投稿を分析し、自然な状態での顧客の声を収集することも効果的です。
また、カスタマージャーニーマップを作成し、顧客が商品と出会ってから購入、使用に至るまでの各段階での感情変化を可視化します。競合他社への顧客反応を観察することで、市場全体での共感ポイントを把握することも可能でしょう。
共感ポイントの抽出では、顧客が本当に困っていること、顧客が理想とする状態、現在の商品・サービスでは満たせない感情的ニーズ、そして顧客が大切にしている価値観に注目します。この段階で重要なのは、表面的な要望ではなく、その背景にある感情や価値観を深掘りすることです。
2.ストーリーテリング・トーン設計の体系化
抽出した共感ポイントをもとに、ブランドとしてのストーリーとコミュニケーショントーンを体系化していきます。ここでは一貫性と継続性が何より重要になります。
ストーリーテリングでは、ブランドの起源・創業ストーリー、商品・サービス開発の背景、社会に対する想いやミッション、顧客との関係性における理想像という4つの要素を整理します。これらの要素が相互に関連し合い、一本の筋の通ったストーリーを構成することが大切です。
トーン設計では、親しみやすさ vs 権威性、カジュアル vs フォーマル、感情的 vs 論理的、個人的 vs 組織的といった軸を明確にします。重要なのは、どちらが良いかではなく、自社のブランドと顧客層に最も適したトーンを一貫して使用することです。
これらの要素を統一し、すべてのコミュニケーションで一貫したブランド体験を提供することで、顧客との信頼関係を築くことができます。ブランドガイドラインとして文書化し、チーム全体で共有することも重要でしょう。
3.タッチポイント設計(SNS・広告・LP・接客)への展開
設計したストーリーとトーンを、顧客との各接点で具体化していきます。各チャネルの特性を活かしながら、一貫したブランド体験を提供することが目標です。
SNSでは日常的な価値観の共有と顧客との双方向コミュニケーションに重点を置きます。商品紹介だけでなく、ブランドの日常や開発の裏側、社会への取り組みなどを発信し、顧客との距離を縮めることが効果的でしょう。
広告では、ブランドの想いを伝える感情的な訴求を中心とします。機能面の説明だけでなく、「なぜこの商品が生まれたのか」「どんな想いが込められているのか」を伝えることで、単なる商品紹介を超えた共感を生み出せます。
LP(ランディングページ)では、商品機能とブランドストーリーを統合し、論理と感情の両面で顧客に訴求します。接客・カスタマーサポートでは、個別対応での共感体験を提供し、一人ひとりの顧客との関係を深めていくのです。
展開時には、各チャネルでの一貫性確保、チャネル特性に応じた表現の最適化、顧客の行動段階に応じた情報提供、継続的な効果測定と改善という4つのポイントに注意する必要があります。
共感マーケティング実践時の落とし穴と注意点
共感マーケティングは万能ではありません。実際に取り組む際によくある失敗パターンを事前に把握し、効果的な施策設計につなげましょう。
企業視点に偏った一方的なメッセージ発信
共感マーケティングでよく見られる失敗が、企業側の想いを一方的に押し付ける「自己満足的なコミュニケーション」です。
この問題は、抽象的で美しい言葉の羅列、企業の自己満足的な表現、顧客の実際の課題から乖離した内容、行動につながらない感情的な訴求のみといった形で現れます。企業が自社の素晴らしさを語ることに夢中になり、顧客が本当に求めている価値から目を逸らしてしまうのが原因でしょう。
改善のためには、顧客の声を起点とした内容構成が重要です。具体性のある表現を使用し、感情と論理のバランスを保ちながら、明確な行動喚起を設定することが重要になります。重要なのは、「感動させること」ではなく「共感してもらうこと」であり、常に顧客の立場に立った表現を心がける必要があります。
共感軸と訴求軸のズレ(ペルソナ不一致)
設定したペルソナと実際の顧客層がズレていると、共感を狙った施策が逆効果になる場合があります。このズレは企業にとって深刻な問題となりがちです。
ズレが生じる主な原因は、理想のペルソナと実際の顧客の乖離、複数のペルソナへの中途半端な対応、時間経過による顧客層の変化、競合の参入による市場環境の変化などが挙げられるでしょう。特に、創業時に設定したペルソナが現在の顧客実態と異なっているケースは多く見られます。
対策としては、定期的な顧客調査の実施が基本となります。データに基づいてペルソナを見直し、セグメント別の施策設計を行い、A/Bテストによって反応を確認することが効果的です。共感マーケティングは正確なターゲット理解が前提となるため、継続的な顧客理解の深化が不可欠といえます。
短期的な成果に偏る施策設計
共感マーケティングは長期的な関係構築を目的とするため、短期的な成果のみを追求すると本来の効果を発揮できません。この問題は多くの企業が陥りやすい落とし穴です。
短期志向の問題点として、表面的な感情的反応のみを狙う、継続性のない一過性の施策、ROIの短期的な判断による施策中止、ブランド一貫性の欠如などが現れます。四半期の売上目標に追われるあまり、共感によって築くべき関係性を軽視してしまうケースが典型的でしょう。
長期視点での設計には、ブランド認知からファン化までの全体設計、段階的な関係深化の仕組み作り、長期的なKPIの設定、継続的な改善プロセスの構築が必要です。共感は「届け方」の技術ではなく、ブランドの「土台設計」そのものであると再確認し、持続的な投資として捉えることが重要になります。