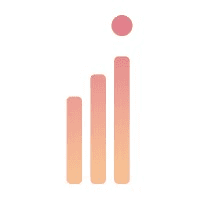デジタルマーケティングとは?基本定義と全体像
まずはデジタルマーケティングの正確な定義と、従来のマーケティングとの違いを明確にしましょう。単なる「デジタル化」以上の本質的な特徴を理解することで、戦略的な活用が可能になります。
デジタルマーケティングの定義
「デジタルマーケティングとは?」と調べると、書籍や記事ごとにさまざまな定義が見られます。ただし、個別の表現に違いはあっても、大枠では共通する要素が存在します。
ここでは、代表的な定義を3つ紹介した上で、共通点を整理してみましょう。
▼デジタルマーケティングの代表的な定義(抜粋)※やや言い回しを変えています
田村修『いちばんやさしいデジタルマーケティングの教本 第2版』インプレス
デジタルデバイスを通じた消費者への情報提供、コミュニケーション、取得したデータの活用など、デジタルならではの特性を生かしながら「売れる仕組み」を作っていくこと
西井敏恭『デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法』翔泳社
マーケティングという大きなフィールドがあり、その中でウェブサイトを中心としたものが「ウェブマーケティング」、アプリからもたらされる位置情報、実店舗のデータ、SNSの投稿など、オンライン/オフライン問わず幅広いデータを活用するものが「デジタルマーケティング」
安岡寛道ほか『デジタルマーケティング2.0』日経BP
デジタルでの売れる仕組み作りのことを指し、そのビジネスを遂行した後、デジタルデータで検証する(次の仕組み作り)までの一連の流れ
▼デジタルマーケティングの代表的な定義(抜粋)

このようなさまざまな解釈をまとめると、デジタルマーケティングとは以下の要素を持つものであると認識できます。
デジタルメディア・テクノロジーを活用するマーケティングのプロセス・手段
自社の商品・サービスと顧客と関係を築き、売れる仕組みをつくるもの
幅広いデータを用いて検証し、商品・サービスを進化させていくもの
▼デジタルマーケティングの定義に共通する3つの要素

デジタルマーケティングは特に、「デジタルメディア・テクノロジーを活用するマーケティングのプロセス・手段」として多くの場面で活用されています。
▼「デジタルマーケティング」をまとめると

「マーケティング」と「デジタルマーケティング」の違い
「デジタルマーケティング」という言葉を正しく理解するには、まず「マーケティング」との違いを押さえることが重要です。両者の本質的な差は、使う媒体がデジタルかどうかという表面的な点にとどまりません。
特に注目すべきは、“計測性”と“柔軟性”という2つの特性です。
媒体の違い以上に大きい、"計測性"と"柔軟性"
計測性の違い
アナログ:
効果の可視化が困難(例:チラシを5,000枚配布しても、実際に何人が読んだかは不明)
デジタル
クリック数、閲覧時間、コンバージョン率など、すべての行動が数値で可視化可能
柔軟性の違い
アナログ:
改善サイクルが長い(印刷物の場合、次回制作まで修正不可)
デジタル:
リアルタイムでの改善が可能(広告文の変更、ターゲティングの調整など)
つまり、デジタルマーケティングの本質的な強みは、
「数値で把握できる」+「すぐに修正・切り替えできる」
この2つを組み合わせることで、仮説 → 実行 → 検証 → 改善 のPDCAサイクルを高速で回すことが可能になります。
結果として、限られた予算や人的リソースでも、マーケティング成果を効率的に最大化できるのです。
デジタルマーケティングとウェブマーケティングの違い
デジタルマーケティングと似た言葉で「ウェブマーケティング」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。この両者は似た言葉で、同じ意味合いで使っている人もいますが、一般的にはウェブマーケティングはデジタルマーケティングの一部とされています。
「デジタル」とは、データを0・1の2進数で表現することやその状態のことを指し、そもそもその定義は広範です。対して、「ウェブ」はインターネットにおいてHTTP、URL、HTMLといった基本技術で構成されるシステムやウェブサイトそのものを指します。
そのため、ウェブマーケティングというと、特にウェブサイトを中心とした施策を中心に考えられることが多いようです。
▼マーケティング施策図解

デジタルマーケティングとウェブマーケティングとの違いについて、定義や歴史的背景も含めた詳しい説明は、「【これで解決】デジタルマーケティングとウェブマーケティングの違いを図解|手法マップ・業種別活用例まで」をご覧ください。

代表的なデジタルマーケティング施策とその特徴
デジタルマーケティングで活用できる手法は多岐にわたります。「どれをやればいいか分からない」という状況を解消するため、各手法の特徴と適用場面を整理し、自社に最適な選択ができるよう解説します。
手法 | 主な目的 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|
運用型広告(リスティング・ディスプレイ・SNS広告) | 顕在層への直接アプローチ | 即効性・リアルタイム調整可能・少額から開始 | 短期間で結果が欲しい場合 |
純広告 | 認知拡大・ブランディング | 条件事前確定・運用調整不要・大規模リーチ | 潜在層への認知度向上 |
SEO(検索エンジン最適化) | 潜在顧客の集客 | 資産型・中長期的効果・ランニングコスト低 | 検索ニーズが明確な商材 |
ウェブサイト改善 | コンバージョン率向上 | 相乗効果・A/Bテスト可能・ユーザビリティ向上 | 既存施策の効果最大化 |
SNSマーケティング | ファン化・認知拡大・コミュニティ形成 | 双方向性・拡散性・低コスト開始可能 | ブランド構築やロイヤリティ向上 |
メールマーケティング | リード育成・既存顧客維持 | セグメント配信・自動化可能・業界選ばず | 検討期間が長い商材 |
アフィリエイト | 成果報酬型の集客 | 専門家活用・無駄コスト削減・成果連動 | 比較検討されやすい商材 |
データ収集・分析 | 施策の効果測定・改善 | リアルタイム分析・ROI算出・改善サイクル | 全施策に必須 |
運用型広告(リスティング広告、ディスプレイ広告、動画広告、SNS広告など)
運用型広告とは、配信開始後も広告文・画像・ターゲティング条件・入札価格などをリアルタイムで変更・最適化できる広告形式です。
従来のテレビCMや新聞広告のように「事前に決めた内容をそのまま掲載する」アナログ広告とは異なり、配信途中でも柔軟な改善が可能な点が最大の特徴です。
特に2020年代に入り、GoogleやMeta(旧Facebook)などの広告プラットフォームでは、「スマートビッティング(入札自動最適化)」「予測コンバージョン(将来的な成果確率をもとに配信最適化)」のようなAIベースの最適化機能の標準装備化が進んでいます。
▼運用型広告の例
ディスプレイ広告(ウェブサイトなどに画像などで表示する広告)
リスティング(検索連動型)広告(GoogleやYahoo!の検索結果画面などにテキストで表示する広告)
SNS広告(X(旧Twitter)やMeta(旧Facebook)などに画像・テキストなどで表示する広告)
▼リスティング(検索連動型)広告・ディスプレイ広告の例(Yahoo!広告)

引用:Yahoo! JAPAN
いずれも、広告主が配信タイミングや予算配分を柔軟にコントロールでき、成果が出ない広告は即時停止、反応の良い広告には追加予算を割くといった運用が可能です。
さらに、年齢・性別・エリア・興味関心など細かなターゲット設定ができる点も、テレビ・新聞など従来メディアにはない強みです。
純広告
純広告は、ウェブメディアやポータルサイトなどが保有する広告枠を事前に予約・買い切りで掲載する広告形式です。「◯日間掲載」「◯万回インプレッション保証」などの条件に基づいて表示回数や掲載期間を確保するスタイルです。
▼純広告の例(Yahoo! JAPANのトップページ右上の枠)

引用:Yahoo! JAPAN
運用型広告と純広告の違い
比較項目 | 運用型広告 | 純広告 |
|---|
配信管理 | 自由に改善可 | 掲載後の調整は基本不可 |
費用形態 | クリック・表示ごとの変動課金 | 期間または表示回数で固定課金 |
柔軟性 | 高(即時変更・停止可能) | 低(事前合意に沿って固定) |
目的 | 効率重視(CV/CPA) | 認知・ブランド想起向き |
運用型広告が掲載期間や予算上限などを自由にコントロールするのに対して、純広告では事前に定めた条件にのっとった掲載枠を買って表示させるという違いがあります。このような費用形態と運用方法の違いから、純広告を「予約型広告」「買い切り型広告」と呼ぶこともあります。
特に近年は、純広告においても「インプレッション保証+一部自動最適化」などのハイブリッド型モデルが登場しており、線引きはやや曖昧になってきています。ただし、「ターゲット精度」「スピード調整」「PDCA運用」などにおいては、依然として運用型広告の優位性が目立ちます。
従来のテレビ・新聞広告や看板広告などもアナログマーケティングにおける純広告の1つです。デジタルマーケティングにおける純広告にはいくつか種類がありますが、例えば以下のようなものがあります。
▼デジタルマーケティングにおける純広告の種類
リッチ広告・ジャック広告(動画やアニメーションなどの演出ができる広告)
記事・タイアップ広告(PR表記付きで記事などのコンテンツの形式で作成される広告)
純広告は、ポータルサイトや大手新聞社といったアクセス数の多いウェブサイトなどに対して必ず広告掲載できるため、特に自社や自社商材をよく知らない潜在層に対しての企業・商品・サービスの認知度向上やブランディング効果を期待できます。
また、広告掲載前に条件が決まっているため、掲載後の細かな運用調整が不要という特徴もあります。
SEO

引用:Google
SEOは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、ウェブサイトを、GoogleやYahoo!などの検索エンジンのアルゴリズムに適した形に調整し、上位表示されるように評価を高める取り組みのことです。
ユーザーが何か課題やニーズを持ち検索したときに最初に表示されるページやコンテンツほど目につきやすくクリックされやすいため、SEOではユーザーのニーズと自社商品が結びつくような記事を作成することを目指します。
運用型広告のように広告出稿のための費用が発生せず、ウェブサイトの配下でページ作成できるので、一度コンテンツを作成して上位表示されれば、ランニングコストなしで成約に至る可能性があります。
ウェブサイト改善
自社のウェブサイトはあるものの、作りっぱなしになっていて成約につながっていないという企業は数多く存在します。ユーザーの求める情報を適切に配置し、成約につながるように改善することもデジタルマーケティングの重要な役割です。
例えば、ユーザーが閲覧・操作しやすいインターフェースに最適化したり、問い合わせや資料ダウンロードのフォームを改善したり、ページの階層を整理したりすることで、視認性・利便性が高まり、デジタルマーケティングの中心として機能できるウェブサイトに生まれ変わります。この際、ユーザーに対して数パターンをテストするA/Bテストや、専門家によるヒューリスティック分析を行うこともあります。
ウェブサイトの改善を運用型広告やSEO、SNSマーケティングなどと合わせて着手することで相乗効果を生み、デジタルマーケティングの効果を高められる可能性があります。
アフィリエイト
アフィリエイトとは、成果報酬型の広告です。運用型広告でもSEOでも活用されます。
アフィリエイトを活用して広告を出稿したい事業主は、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)と呼ばれる広告とメディアの仲介プラットフォームに登録します。アフィリエイターと呼ばれるメディア運営者が登録された広告案件を見て、自身のウェブサイトやブログなどに商品・サービスの広告掲載を行います。アフィリエイターの広告経由で成約が発生したら、広告主は報酬を払う仕組みです。
▼アフィリエイトの仕組み

アフィリエイトを活用することで、企業には集客を専門家に任せながら、成果につながらない無駄なコストを減らせるメリットがあります。また、報酬額を変動させることで、目標数値に合わせた費用調整も可能です。
アフィリエイトは、企業規模や業界を問わず活用されていますが、特にウェブで検索して比較されやすい商材に向いています。
SNSマーケティング

引用:Instagram
SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)・Instagram・Meta(旧Facebook)・TikTokなどに代表されるSNSで、広告配信やアカウント運用を行う手法です。各SNSは基本的に無料でアカウントを開設できるため、中小企業でも取り組みやすいマーケティング手法です。
SNSの特徴はシェアや拡散であり、コンテンツがターゲットユーザーにはまれば莫大な効果を生み出す可能性もあります。インフルエンサーを活用し、バズを狙うこともSNSマーケティングのひとつです。また、ユーザーや顧客と直接コミュニケーションを取れれば、ロイヤリティ向上にも役立ちます。
メールマーケティング
メールマーケティングとは、その名のとおり、メールを活用したマーケティング施策です。
見込み客や顧客のリストへの一律のメールマガジン送付だけでなく、ユーザー属性に合わせた内容別配信、ユーザーの行動・心理に応じた自動配信なども可能です。内容は企業のニュースや、商品紹介、セミナーの案内、コラム、クーポン配信、製品フォローなど多岐にわたります。
メールアドレスはほとんどの人が持っているため、商材や業界を選ばず使いやすく、導入のハードルが低い特徴があります。CRM・MA・配信ツールなどを活用することで効率的かつ効果的な実施が可能です。
これらの施策はそれぞれに強みがありますが、単体で成果を保証するものではありません。
言い換えれば、施策はあくまで“道具箱”の中のツールに過ぎず、戦略という設計図があってこそ本来の力を発揮します。
次の章では、なぜ成果が出ないのかという典型的な失敗パターンを整理し、そこから「戦略的にどう組み合わせるべきか」を解説していきます。
なぜ成果が出ないのか|よくある3つの構造的なミス
多くの企業がデジタルマーケティングに取り組んでいますが、必ずしも期待通りの成果を上げられているとは限りません。
その要因は、ツールや施策の不足ではなく、戦略設計そのものに潜む構造的なミスにあることがほとんどです。
ここでは、よくある失敗パターンを整理しながら、実務でどう回避するべきかを解説します。
手段の目的化
「SNSはやっています」「広告は出しています」──これは一見すると前向きな取り組みに見えますが、
「何のためにやっているのか?」という問いに答えられない状態であれば、それは“手段の目的化”に陥っている可能性があります。
典型的な例:
Instagramの投稿数だけを追っており、成果とのつながりが見えない
広告のクリック数は把握しているが、資料請求や購入には結びついていない
SEO順位は改善しているが、問い合わせや売上の変化が見られない
解決のポイント:
単に「行動量(アクティビティ)」を追いかけるのではなく、
その行動が、どのように成果に結びつくのかを明確にする必要があります。
▼【デジタルマーケティング】実務での進め方(例)

このように「活動 → 成果」の流れを一連で設計・可視化しておくことで、
「SNS投稿しているけど売上に貢献していない」
「広告費を使っているがROIがわからない」
といった状況を防ぐことができます。
ペルソナ不在のまま進めている
「ターゲットは20〜40代の男女です」──このような曖昧なターゲット設定では、どんなに優れた施策も効果を発揮できません。
なぜペルソナが重要なのか:
メッセージの刺さり方が変わる
利用するチャネルや媒体が変わる
コンテンツの内容や表現方法が変わる
具体例の比較:
曖昧なターゲット:「30代の働く女性」 明確なペルソナ:「32歳、マーケティング部門、子育てと仕事の両立に悩んでいる、効率化ツールに関心が高い、InstagramとTwitterを日常的に利用」
この違いによって、刺さるメッセージも配信すべきチャネルも大きく変わります。
チャネルごとの分断
ウェブ広告とSNSの担当者が別々で連携がない、営業部門とマーケティング部門でデータ共有ができていない──このような状況では、顧客体験が「ちぐはぐ」になってしまいます。
顧客視点での問題:
SNSで興味を持った商品について、ウェブサイトで詳細を調べようとしたら情報が統一されていない
広告をクリックしたランディングページの内容が、広告の訴求と異なる
問い合わせ後の営業担当者が、これまでの接点を把握していない
解決のポイント:
顧客の行動フロー全体を俯瞰し、チャネル連携の設計図を描くことが必要です。各タッチポイントでの体験を一貫性のあるものにすることで、コンバージョン率は大幅に改善します。
自社に合ったデジタルマーケティング戦略をつくるための5ステップ
ここからは実践編です。デジタルマーケティングを「なんとなく」ではなく「戦略的に」進めるための具体的な手順を、5つのステップで解説します。多くの企業支援で実証済みのプロセスなので、自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。
STEP1|目的・課題の明確化
戦略設計の第一歩は、「何を達成したいのか」を数値で明確にし、チーム全体で共通認識を作ることです。
BtoB企業の目的設定例:
今期中にMQL(マーケティング適格リード)を月間50件獲得したい
既存顧客からのアップセル・クロスセル売上を前年比120%にしたい
新サービスの認知度を業界内で30%まで高めたい
営業効率を改善し、商談化率を現在の10%から15%に向上させたい
BtoC企業の目的設定例:
ECサイトの月間売上を前年同月比150%にしたい
新商品のリピート購入率を40%以上にしたい
ブランドの認知率を主要ターゲット層で25%まで向上させたい
顧客獲得単価(CPA)を現在の8,000円から5,000円に改善したい
この段階で、予算上限・人的リソース・達成期限も併せて明確にしておくことが重要です。
STEP2|現状分析
自社・競合・市場の現状を客観的に把握するため、フレームワークを活用した分析を行います。
活用すべきフレームワーク:
3C分析:
Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)
SWOT分析:
Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)
STP分析:
Segmentation(市場細分化)、Targeting(標的市場選定)、Positioning(位置づけ)
デジタル領域での現状把握項目:
自社ウェブサイトのアクセス状況(Google Analytics等で確認)
競合他社のデジタル施策調査(広告出稿状況、SNS活用状況等)
既存顧客のデジタル行動パターン(アンケートやインタビューで把握)
STEP3|戦略・スケジュール策定
目標と現状のギャップを埋める戦略を、予算・リソースに合わせて具体的に設計します。
戦略設計の要素:
ターゲット・ペルソナ設定:「誰に」を明確化
カスタマージャーニー策定:「どのような体験を提供するか」を設計
KPI設定:「何をもって成功とするか」を数値化
予算配分:「どの施策にどれだけ投資するか」を決定
STEP4|手法の選択
戦略を実現するための具体的な手段を、優先順位をつけて選択します。
施策別KPI設定例:
施策 | KPI例 |
|---|
運用型広告 | インプレッション数、クリック単価、コンバージョン単価、クリック率 |
SEO | 検索順位、オーガニック流入数、滞在時間、コンバージョン数 |
ウェブサイト改善 | 直帰率、ページ滞在時間、コンバージョン率、フォーム完了率 |
メールマーケティング | 配信数、開封率、クリック率、配信停止率 |
SNSマーケティング | フォロワー数、エンゲージメント率、ウェブサイト遷移数、UGC数 |
STEP5|施策実行・振り返り
施策の結果を定期的に振り返り、目標達成に向けた改善を継続的に行います。
振り返りのサイクル:
週次:各施策の数値確認、緊急対応が必要な課題の特定
月次:KPI達成状況の確認、施策の優先順位見直し
四半期:戦略全体の見直し、予算再配分の検討
改善のポイント:
データに基づいた客観的な判断を心がける
短期的な数値変動に一喜一憂しない
ボトルネックを特定し、全体最適を図る
必要に応じて外部パートナーとの連携を検討する
デジタルとアナログの"使い分け方"を設計する視点
デジタルマーケティングは、既存の営業活動や展示会などを排除するものではありません。むしろ、デジタルとアナログを戦略的に組み合わせることで、より大きな相乗効果を生み出すことができます。統合的なマーケティング設計の考え方を解説します。
営業・展示会とデジタル施策の連携例
デジタルマーケティングは、既存の営業活動や展示会などのアナログ施策と対立するものではありません。むしろ、相互に補完し合う関係として設計することで、より大きな効果を生み出せます。
展示会 × デジタル連携の具体例:
事前:展示会来場予定者にターゲティング広告を配信
当日:名刺交換した見込み客のメールアドレスを収集
事後:展示会参加者リストを活用したリターゲティング広告を2週間配信
継続:興味を示した見込み客にはメールマガジンで定期的な情報提供
この連携により、展示会の効果を最大3倍まで高めることが可能です。
営業活動 × CRM連携の例:
営業担当が訪問前に、見込み客のウェブサイト閲覧履歴を確認
提案後は、関連資料をメールで送付し、開封・クリック状況を営業が確認
商談が長期化している見込み客には、リターゲティング広告で継続的にアプローチ
リード獲得から育成までの全体設計
BtoB企業の場合、リード獲得から受注までのプロセスを一気通貫で設計することが重要です。
統合的なリード管理の流れ:
リード獲得:
SEO、広告、SNS、展示会など複数チャネルから
スコアリング:
行動データに基づいて見込み度を数値化
ナーチャリング:
メール、コンテンツ、リターゲティング広告で育成
営業連携:
スコアが一定値を超えた時点で営業にパス
継続フォロー:
受注後も継続的な関係維持とアップセル提案
今後の主流は"統合型マーケティング"
現在のマーケティングトレンドは、「デジタルかアナログか」ではなく、「いかに一貫した顧客体験を提供するか」に移行しています。これは統合マーケティングコミュニケーション(IMC)と呼ばれる考え方です。
IMCの基本原則:
すべてのタッチポイントでメッセージの一貫性を保つ
顧客の行動データを統合的に管理・活用する
チャネル間でのデータ連携を前提とした設計にする
この考え方に基づいて施策を設計することで、顧客満足度と事業成果の両方を向上させることができます。