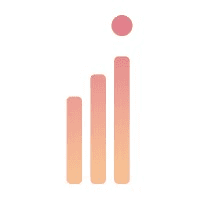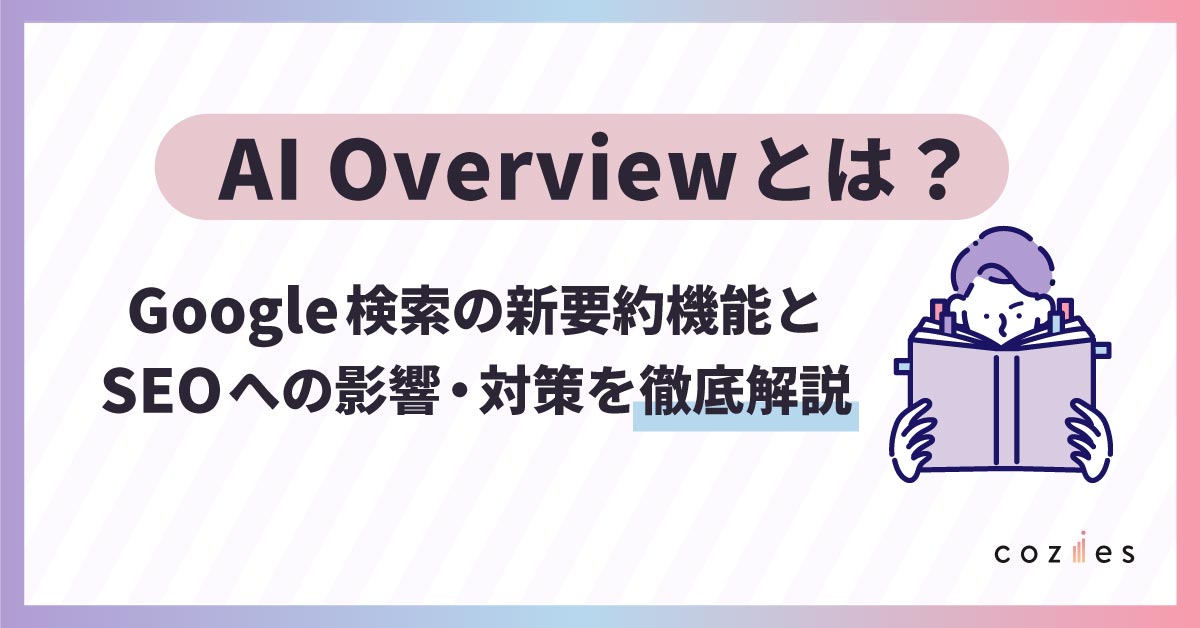マーケティングとは
マーケティングにはさまざまな定義があり、一言で言いあらわすことは困難です。
広義では、「自社の商品やサービスの販売や認知を促進し、顧客との関係を継続していくための総合的な活動」として受け入れられています。
なぜマーケティングは必要なのでしょうか。
競争が激化している現代では、単に良い商品を作るだけではなく、それを顧客に「欲しい」と「思わせる」ことが必要です。また、購入してもらった先にある、顧客との信頼関係構築という工程も欠かせません。これにより、新たな購入・利用の可能性、ブランド価値の向上が見込めます。
マーケティングとセールスの違い
先ほど説明したマーケティングに近い活動として、セールスが挙げられます。
セールスは、商品やサービスを顧客に直接売り込む行為を指し、短期的な売り上げの向上を目的とすることが一般的です。「営業」のイメージに近いです。
一方、マーケティングは「売れる仕組みをつくる」ということに重きがおかれています。そのため、市場調査・商品企画・プロモーション設定など、その活動内容も多岐にわたります。
マーケティングの最新情報
企業側が市場に働きかけるための活動、というイメージが強いマーケティングですが、近年はその定義が変化しつつあります。
参考までに、2024年1月に刷新された、日本マーケティング協会によるマーケティングの定義を紹介します。
▼マーケティングの定義(2024年)
(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。
注 1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。
注 2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。
注 3) 構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。
引用:公益社団法人日本マーケティング協会「34年振りにマーケティングの定義を刷新」
マーケティングの種類と特徴
マーケティングがどのようなものかイメージがつかめたところで、「実際にどんな手法があるのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
この章では、主なマーケティングの種類について紹介します。
デジタルマーケティング
デジタルマーケティングは、インターネットを活用し、ウェブサイト、SNS、メール、オンライン広告などを通じて行うマーケティング手法です。
自社・競合問わず、企業が収集した膨大な顧客データを収集・分析し、それをマーケティング戦略に生かすことができます。
たとえば、GoogleやMicrosoft、Metaの媒体を利用して行えば、それらの膨大な顧客データを利用できるため、高いターゲティング精度が特徴です。分析ツールを利用することで、容易な効果測定や詳細なレポートの確認などが可能です。
具体的には、顧客の行動や嗜好をもとにした予測マーケティングや、ターゲットをより絞って、個人に焦点をあてたパーソナライズマーケティングなどがあります。
ダイレクトマーケティング
ダイレクトマーケティングは、顧客に直接アプローチする手法になります。メール、電話、ダイレクトメールなどを活用します。近年ではSNS上のダイレクトメッセージなども活用されています。
双方向のコミュニケーションをとりやすく、効果測定を行いやすい(問い合わせや反応があるかなど)点が魅力ですが、かかる時間や労力、費用、効率などを考えると、多くの顧客には届きにくい点がデメリットです。
コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングは、顧客にとって価値のある情報を提供し、信頼関係を築くことで購買意欲を高める手法です。
一般的なコンテンツの例としては、ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなどがあります。
即座に顧客獲得にはつながりにくいため、本業の片手間に行える余裕がなければ難しい手法です。
エクスペリエンスマーケティング
エクスペリエンスマーケティングは、顧客に商品やサービスを実際に体験してもらうことで、ブランド価値を伝える手法です。単なる商品の販売だけでなく、顧客との感情的なつながりを築くこと(ブランドへの愛着やロイヤリティなど)を目的としています。
イベントやポップアップストア、ワークショップ・セミナー、使用期間の提供などが主な手法です。
マーケティングの基本プロセス
この章では、実際にマーケティングを実施する際、どのような手順を踏んで行うのか説明します。

市場調査・分析(セグメンテーション)
まずは、市場の調査と分析から始まります。モニターへのアンケートや信頼性のあるデータを調査するなどが主な方法です。
マーケティングにおいては、「誰に」「何を」「どのように」提供するかが重要な指標となってきます。これは、どのプロセスにおいても常に考えなければならないことです。
市場調査・分析では、「誰に」「何を」を決めることができます。
セグメンテーションと呼ばれる、共通のニーズや特性をもつ顧客グループ(セグメント)を特定する作業では、ターゲットとしたい顧客層がどのような人々かを明確にします。
戦略設計
次は、マーケティング戦略を練ります。このフェーズでは主に、ターゲティング、ポジショニング、マーケティングミックスを行います。
市場の調査と分析で得た結果をもとに、セグメンテーションを実施しました。ここからさらに、ターゲットとしたい顧客層がどのような人々かを明確にします。
ターゲティングは、セグメンテーションで特定したセグメントの中から、「年齢」「性別」「家族構成」「収入」「趣味」などの属性をもとに、さらに細かく商品やサービスに適した顧客を選定する作業です。
次に、決定したターゲット市場において、自社および自社商品はどのような位置(「安くて大量」「高いけど質が良い」など)にいるのか、あるいはいたいのかを考えます。この作業がポジショニングです。
自社商品の方向性が決まれば、それをどのようにプロモーションするのか、流通させるのかを決定します。この段階で、さまざまな分析手法を用いたマーケティングミックスにより、具体的な実行方法に落とし込んでいきます。価格設定も戦略の一つです。
これまでで、「誰に」「何を」「どのように」届けるのかが決定します。
これらのフェーズは、「ここからそこまでが〇〇」と一概に言えるものではなく、さまざまな考え方があります。
例えば、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングは、それぞれの頭文字をとってSTP分析と一括りにされることもあります。

しかし、本質は大きく変わりませんので、あまり心配する必要はありません。
実行・効果検証
立て終わった戦略を実行し、その効果を分析します。
プロモーション手法がデジタル広告であれば、広告の運用が実行にあたり、商品の売り上げ状況、広告のクリック数やそこから商品の購入に至った数など、数値を確認・分析するのが効果検証にあたります。
事前に定めた目標に対して成果を検証し、その成果にいたった背景の考察や施策の適切性の評価、課題の発見などをして、PDCAサイクルを回すようにしましょう。
短期的な売り上げや効果も大切ですが、「目標としていたターゲットに届いたか」「何か想定外の顧客の動きはないか」など、長期的な視点を意識することが大切です。
マーケティングの戦略決定のためのフレームワーク
この章では、先ほど述べたマーケティング戦略について、市場の分析や商品の方針決定など、実際の分析手法について解説します。
市場分析やターゲティングなど、各段階で活用してみてください。
3C分析
3C分析のCは、「顧客(Customer)」、「自社(Company)」「競合(Competitor)の3つを指します。主に業界環境を分析するための手法です。

それぞれ3つの要素を分析することで、自社の競争優位性を明確にするものです。
「顧客」では、市場規模や成長性、顧客のニーズや購買行動など、自社が誰を相手にするのかについて考えます。
「自社」は、市場シェア、ブランドイメージ、リソース、商品やサービスの特徴を評価し、自社の位置づけを把握します。
「競合」では、競合他社の動向、シェア、強みや弱み、市場への参入障壁などを分析します。自社がどう差別化して成功できるか考えるために必要な要素です。ウェブサイトやカタログをチェックしたり、実際に商品を使ってみるという手法があります。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社の内部環境と外部環境について、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの要素について考察するフレームワークです。
SWOT分析
| プラス要因 | マイナス要因 |
内部環境 | 強み(Strength)
自社や自社製品の強み | 弱み(Weakness)
自社や自社製品の弱み |
|---|
外部環境 | 機会(Opportunity)
自社にとってプラスに働く外部環境 | 脅威(Threat)
自社にとってマイナスに働く環境 |
|---|
SWOT分析を行うことで、既存事業の弱みを把握し、改善点を探すことができるほか、将来的なリスクについても事前に認識することができます。
SWOT分析は多くの企業がマーケティングや戦略立案に役立てており、「誰に」「何を」届けるのか検討する際に、非常に有効な考え方になります。
4P・4C分析
4P・4Cは、具体的な施策を実行する段階での分析手法です。両者は同じフレームワークで行われますが、「企業視点」か「顧客視点」かという違いがあります。
まずは4P分析について説明します。

4PのPは、「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販売促進(Promotion)」です。
どのような商品を「いくらで」「どういった経路で」「どのような手法で販売促進するか」といった要素から、施策を検討します。

一方、4C分析は4P分析と似たような観点を異なる視点から分析する手法になります。
4CのCは、「顧客にとっての価値(Customer Value)」「コスト(Cost)」「利便性(Convinienece)」「コミュニケーション(Communication)」です。
商品がターゲットにとってもたらす価値、ターゲットにとってのコスト、購入しやすい環境か、必要な情報が届いているか、といった考え方になります。
企業はなかなか顧客視点で考える機会はないため、2つの視点から分析することで、新たな改善点や妥協点が見つかるかもしれません。
マーケティング成功のためのポイント
ここまで、マーケティングの手法や実施方法について説明してきました。
この章では、マーケティングを成功させるためのポイントを紹介します。
顧客理解
まず欠かせないのは顧客理解です。ターゲットとなる顧客のニーズや行動を深く理解しているか否かが、戦略の出来を左右します。
顧客の理解には、大雑把な属性について把握するのも良いですが、「ペルソナ」というより具体的な人物像に落とし込むことで、理解した「つもり」を防ぐことができます。
ペルソナについては、「ペルソナの作り方は?マーケティング業務で活用するポイントも解説」の記事をご覧ください。
明確な目標設定と振り返り
目標設定と振り返りも、顧客理解と同じく戦略の基盤となるポイントです。
たとえば、最終的なゴールが「認知向上」なのか「売り上げ向上」なのかによって、アプローチはかなり異なってきます。
最終的に達成したい目標はKGI(Key Goal Indicator)と言い、単純に「売り上げ向上」だけでなく、「市場シェア〇〇%達成」「利益率月比〇〇%増」など、より具体的にしましょう。
KGIとは別に、KPI(Key Performance Indicator。KGIを達成するための中間目標)も設定することで、途中経過の把握・分析やそれによる施策の変更も容易になります。