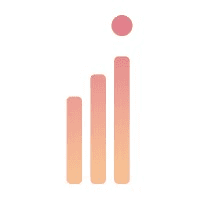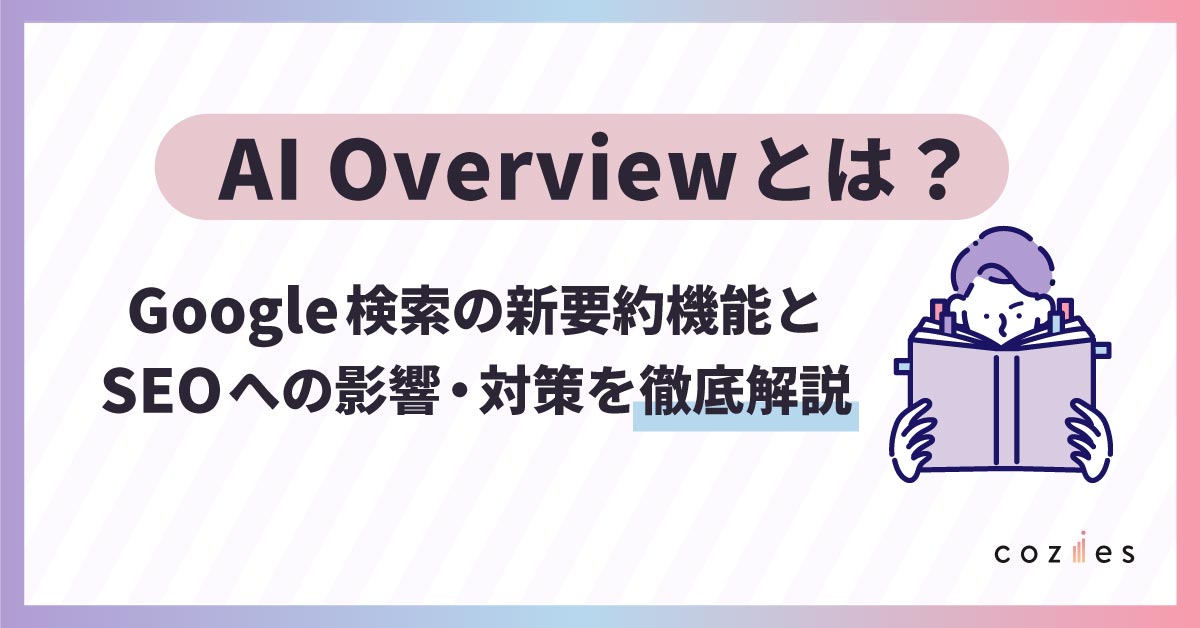生成AIとは
生成AIとは、簡単に言うと「あなたの代わりに文章を書いたり、絵を描いたりしてくれるデジタルアシスタント」のことです。
従来のコンピュータは、人間が事前に決めたルールに従って作業をしていました。しかし生成AIは違います。人間が「こんなものを作って」とお願いすると、その場で新しいコンテンツを作り出してくれます。
代表的な生成AIに「ChatGPT(チャットジーピーティー)」があります。例えば、ChatGPTに「来週の会議用に売上報告書の構成を考えて」と入力すると、以下のような提案をしてくれます。
今月の売上実績
前月との比較分析
好調だった商品・サービス
課題となった点
来月の改善策
画像生成AIも同様です。例えば、「新商品発表会の会場レイアウト図」と入力すると、プレゼンで使える図解を作成してくれます。
従来のAIとの違い
従来のAIと生成AIの違いは、以下のとおりです。例えば、従来のAIに「プレゼン資料」と入力すると、インターネット上にあるプレゼン資料を検索して表示します。しかし生成AIに「新商品発表のプレゼン資料の構成を考えて」と入力すると、あなたの企業や商品に合わせた構成案を一から作成してくれます。
この違いが、なぜ今生成AIがこれほど注目されているかの理由です。単に情報を探すだけでなく、新しいものを「創り出す」ことができるからです。
従来のAI:「検索・分析型」
Google検索:入力したキーワードに関連するウェブページを探してくる
音声認識:話した言葉を文字に変換する
画像認識:写真に写っているものが何かを判別する
生成AI:「創造・制作型」
文章生成:指示に基づいて新しい文章を作成する
画像生成:説明に基づいて新しい絵や写真を作成する
アイデア提案:課題に対する解決策を複数提案する
生成AIでできること|あなたの仕事にどう役立つ?
生成AIが仕事にもたらす変化を、具体的な場面でご紹介します。
メール文の下書き
「この内容、どう伝えたらいいかな……」と迷うことはありませんか。
生成AIなら、伝えたい要点を入力するだけで、自然で丁寧な文面のたたき台をすぐに作ってくれます。
例えば、ChatGPTに以下のように入力したとします。
「取引先のA社に新しいサービスを提案するメールを作成してください。サービス名は『効率化サポート』で、作業時間を30%削減できることを丁寧に伝えたいです。」
すると、以下のように、メールの文章が作成されます。

提案資料のアイデア出し
「来月の企画会議で新しい提案をしなければならないが、アイデアが思い浮かばない」そんな時も生成AIが力を発揮します。
例えば、「従業員のモチベーション向上のための社内イベントのアイデアを10個提案してください。予算は50万円以内で、参加者は100名程度です。」と入力すると、以下の画像のようにアイデアを提案してくれます。

マニュアルの作成補助
新しい業務マニュアルや手順書の作成も、生成AIが得意とする分野です。
例えば、「新入社員向けの電話対応マニュアルを作成してください。基本的な受け答えから、クレーム対応の初期段階まで含めてください。」と入力すると、以下の画像のようにマニュアルが作成されます。

今日から使ってみる!|3ステップで生成AI体験
ここまで、生成AIについて説明してきました。本章では、生成AIを実際に体験するための手順を3ステップでご紹介します。

Step1:ChatGPTにアクセスする
公式サイトはこちら: https://chat.openai.com
メールアドレスとパスワードを登録すれば無料で使えます(GoogleアカウントでもOK)。
※スマホでもパソコンでも使えます。

Step2:「おはよう」と打ってみる
ログインができたら、画面下の入力欄に「おはよう」と入れてみてください。
すると、「おはようございます、〇〇さん!今日も何かお手伝いできることがあれば、何でも言ってくださいね」 というように、ChatGPTが返事をしてくれます。
初めの一歩はこれで完了です。

Step3:仕事でよくある質問をしてみる
慣れてきたら、実際の仕事で使えそうな質問をしてみましょう。
以下は質問の例です。
レベル1:簡単な質問
「効率的な会議の進め方を教えて」
「メールの件名で注意すべき点は?」
「プレゼンで緊張しない方法を教えて」
レベル2:より具体的な質問
「新商品のキャッチコピーを3つ考えて」
「売上が下がった時の改善策を5つ提案して」
「チームのコミュニケーションを活発にする方法を教えて」
レベル3:実践的な作業依頼
「来週の営業会議のアジェンダを作成して」
「顧客満足度向上のためのアンケート項目を考えて」
「新入社員歓迎会の企画案を提案して」
質問のコツは、具体的に状況を説明することです。
「〇個提案して」のように数を指定したり、「〇〇の業界で」「〇人の部署で」など条件を追加することをおすすめします。
以下のように具体的に質問すると、より実用的な回答が得られます。
例:「IT企業の営業部(10名)で、月末の売上達成のためのモチベーション向上策を5つ提案してください。予算は5万円以内でお願いします。」
よくある不安とその答え
生成AIに興味はあっても、「本当に使って大丈夫なのか…?」という不安は誰にでもあります。
ここでは、よくある4つの疑問にお答えします。少しでも安心材料になれば幸いです。
AIを使っても仕事は奪われない?
「AIが人の仕事を奪う」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。
しかし、実際には、AIは「代わりにやってくれる存在」ではなく、「支えてくれる存在」です。
AIが代替する作業の例
定型的なデータ入力
簡単な文書作成
基本的な情報収集
単純な計算作業
人にしかできない仕事
創造的な判断
複雑な問題解決
顧客との信頼関係構築
戦略的な意思決定
感情に寄り添う対応
たとえば、議事録をまとめたり、提案資料のたたき台を作ったり、時間をかけていた部分をAIが手伝ってくれることで、本当に大事な判断や対話に集中できるようになります。
セキュリティやプライバシーは大丈夫?
基本的なルールを守れば、安全に利用できます。
生成AIに情報を入力するのは少し不安…という方もいますが、正しく使えば大きなリスクはありません。
企業で導入する場合には、セキュリティが強化された「法人向けプラン」も用意されています。
生成AIを安全に使うための注意点をご紹介します。
入力を避けるべき情報
顧客の個人情報
自社の機密資料
契約書の内容や金額
パスワードやID情報
安心して使うための4つのルール
機密情報は入力しない
顧客名・企業名は「A社」「B氏」などに置き換える
数字や実名など固有情報は避ける
最終的な判断や提出物は必ず人間が確認する
お金はかかる?無料で使えるの?
多くの生成AIツールは、無料プランが用意されています。
たとえば、ChatGPTの無料版は、メールアドレスの登録だけですぐに始められます。
「まずは試してみたい」「本格導入はこれから」という方は、まずは無料プランを使うことをおすすめします。
使ってみて「もっと使いたい」と思えば、有料版に移行することもできます。有料版では、回答速度が速くなり、利用回数制限もなくなるため、業務での本格活用が可能になります。
技術の知識がないと使えない?
「AIの利用にはプログラミングが必要なのではないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、普段メールやインターネット検索を使っている方であれば、生成AIはすぐに使いこなせます。
ChatGPTは、LINEのように話しかけるだけで答えが返ってくる感覚です。
難しい設定や操作は不要で、「こんにちは」のように呼びかけたり、質問や依頼をしたりできれば利用できます。
これからどう学ぶ?1ヶ月の成長ロードマップ
生成AIに興味はあるけれど、「すべてを一度に覚えるのは無理…」と思うかもしれません。しかし、そんな心配は必要ありません。
大切なのは、一度に完璧を目指さず、段階的に慣れていくことです。
本章では、無理なく生成AIを理解し、実務で使えるようになるための「1ヶ月のロードマップ」をご紹介します。
【今日覚える】基礎知識の確認
まずは、以下の点を理解してください。
生成AIとは「文章や画像などを自動で“つくる”AI」のこと
代表的なツールにはChatGPTなどがある
「こんにちは」と打つだけでも使い始められる
無料で始められる生成AIが多い
日本語で質問できる
機密情報は入力しない
今日やるべきアクション
ChatGPTのアカウントを作成する
「おはよう」と入力して返答を確認する
「効率的な仕事の進め方を教えて」と質問してみる
【1週間後に試す】実践体験
次は、実際に少しずつ使ってみましょう。以下のようなテーマで、毎日1つずつ話しかけてみることが重要です。
1回30秒でもいいので使ってみましょう。「使ってみた」という経験が何よりの学びになります。
「メールの下書きを考えて」
「会議の要点を3行にまとめて」
「新商品のキャッチコピーを考えて」
「業務改善のアイデアを出して」
「報告書/提案書の構成を作成して」
【1ヶ月後の目標】定着・発展
1ヶ月後には、こんな姿を目指してください。
この段階では、「AIを使える人」として周囲から一歩先を行っている状態です。
業務の中で「これもAIに任せてみようかな?」と考える余裕も出てきます。
ChatGPTを使って「業務の一部を任せている」状態
同僚に「AIってどう使えばいいの?」と聞かれて答えられる
「もっと活用できそう」と自然に感じられている
また、以下のようなことにも挑戦してみてください。
具体的で詳細な質問ができるようになる:「〇〇業界の〇〇職で、〇〇という課題を解決するために、〇〇という条件下で、〇〇の形式で提案してください」
複数のAIツールの使い分けをする:ChatGPT、Google Bard、画像生成AIなどそれぞれのツールの強みを理解し、目的に応じて使い分ける。
チーム・部署で活用する:部下に生成AIの使い方を教えたり、チームでの「AIの使い方ルール」を話し合う